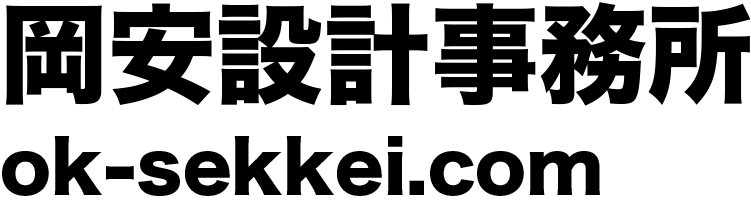食品工場分野の建築設計、設備設計、エンジニアリングを中心に業務を行います。
食品安全について、レクチャーやセミナーを開催します。
植物工場建設、栽培設備、栽培方法、品質管理、マーケティングなども業務分野です。
フードセーフティジャパン2025で企画したセミナーの
概要、資料、いただいたコメントを掲載しました。
調査・レクチャー業務
設計、調査、改善、レクチャー、監査などの業務を行います。
業務内容
食品製造工場の結露防止や防虫、発酵設備の温湿度管理などの調査と現状把握、改善計画、維持のためのレクチャー・セミナ-・相談などをお引き受けしています。
およそ30年500件ほどの実績をもとずく実践的・具体的な知見・対策をお持ち帰りいただけます。
設計の説明
食品工場設計
食品工場設計については、建築設備、生産設備、従業員管理を含めたHACCPなどの食品安全規格に配慮した計画を行います。とくに近年、食品安全の観点から温度帯などの仕様を変更する改修について、既存設備を考慮した計画が必要になっています。
いままでダウンロードの多い、食品製造工場の設計手順(前編)(後編)(実践編)~HACCPの考え方を取り入れた工場設計~はコラムを参照ください。
食品製造工場の設計手順(設計・前編)
食品製造工場の建設は、肉、魚や野菜といった原材料を安全に調理し、包装し出荷する工程についていくつかの角度から検討して工場設計に反映しています。
本編ではHACCPをベースとした食品製造工場レイアウトから食品製造の危害要因への考慮、温度管理による室内環境の維持について記述します。
食品製造工場の設計手順(設計・後編)
後編は、工場設計を構成する要因について記述します。
食品製造工場の建設は、食品を安全に調理し、包装し出荷する工程について、計画時から設計、機器選定、施工に至るまで配慮する項目が多岐にわたります。
換気、エアバランス、清浄度、給排水、防虫、と順を追って説明していきます。
食品製造工場の設計手順(実践編)
食品製造工場の設計を実際の設計図面に落とし込むには、製造品目や事業者毎の製造方法、従業員配置などを元に設計数値として反映していきます。
同じ製造品目でも、消費期限の設定によって管理温度が違い、製造方法によって在室人員などの生産室の条件が変わります。
エネルギー管理の考え方から配管の材質まで建築設備部分の設計について説明します。
エアバランス(陽圧)調査
建築的にはHACCPの要点としてゾーニングや陽圧化を上げる設計者が多いですが、新築時に部屋を閉め切った状態での陽圧化を実現することを目的としている設計者が多いのが現状です。製品や従業員が常に入退室する状態であったり、設備を追加した状態で経年でのエアバランスを保つ必要があります。
チルド食品工場の空調、換気実施設計
食品製造工場の建設は、肉、魚や野菜といった原材料を安全に調理し、包装し出荷する工程についていくつかの角度から検討して工場設計に反映しています。
本編ではHACCPをベースとした食品製造工場レイアウトから食品製造の危害要因への考慮、温度管理による室内環境の維持について記述します。
恒温恒湿設備、発酵庫設計
恒温恒湿設備や発酵庫は、温度誤差をほとんどなくして、平面、立面で均一な温湿度分布を達成する必要がります。食品においては1個当たりの単価が100円であったりする日々何万個という製品が通過する設備が多く存在します。設備費用をかけずに広い範囲で均一な設備を設計する必要があります。また、設備の経年劣化による制御の逸脱も原因を究明し、適切に復旧する必要があります。
恒温恒湿設備・発酵庫
温度と湿度を一定に保つ設備や部屋を恒温恒湿設備と呼びます。 事務室や住宅などでも温度を25℃程度に保つために空調機を設置します。ただ、一般的な空調機は上昇した温度を下げたり、降下した温度を上げることはできますが、すでにその時点で3℃から5℃といった温度差が発生しています。
結露調査・結露対策
食品分野の結露を扱います。温度帯の違う部屋が多数存在し、空気の流れも複雑で、建材の断熱が影響する部分はかなり限定的です。夏季、冬季、室内外を含めた検証と製品や従業員の移動による温湿度環境の変化を総合的に判断し、複数存在する結露の原因を調査し、対策案を提示します。
食品製造設備の衛生管理(陽圧化と結露)
食品製造施設は食品の安全性や品質保持の精度が上がり、低温作業室や冷蔵室の割合が増えてきています。
そのような施設で発生する建材の腐食や黒カビ、水滴の付着の原因を特定することは難しくなっています。
そうした低温作業室や加熱を行う調理室など特殊な条件の作業室の不具合事例や改善事例を説明していきます。
食品安全(HACCP・JFS)診断
環境、使用水、原料加工、生産、包装といった工程で建物設備費関連する食品安全について診断し、提案します。
施設の維持管理が食品安全に果たす役割
はじめに
施設の維持管理が食品安全に果たす役割として、水質や空気の気質、温度管理といった分野での食品危害のリスクを低減させるために行っている取組み、安定的な維持管理の方法などを記します。
設備保全の範囲
ISO/FSSC22000における前提条件プログラム(Prerequisite Program)の一部として、規格要求事項:8.2.4 PRP(s)を確立する場合に組織が考慮しなければならない事項に該当する設備、そのうち建物などに付随する設備を想定します。
植物工場設計・マーケティング
植物工場「ビタミンファーム」が2014年に操業開始したことに伴い、農林水産省フードコミュニケーションプロジェクトで植物工場生産者として、植物工場設備、野菜栽培、品質管理、マーケティングについて食品企業の専門家のみなさんにセミナーを主催しました。コンビニエンスストアで販売されるサラダやサンドイッチに使用される原材料として、農薬やその他の薬品の使用や生産者のリスクなどを細かく開示し、解説しました。食品企業のみなさんの視点から、GAPなど安全規格に沿った工程を組み立てていきます。
農林水産省フード・コミュニケーション・プロジェクト資料_1(PDF版)
第2回植物工場勉強会
開催日時:平成27年9月1日(火曜日) 14:00~17:30
農林水産省フード・コミュニケーション・プロジェクト資料_2(PDF版)
中食における野菜加工実情と消費者のニーズ
1.中食原材料としての野菜 2.サンドイッチ・サラダの開発工程 3.中食商品への消費者のニーズ 4.野菜の調達方法 …
農林水産省フード・コミュニケーション・プロジェクト資料_3(PDF版)
平成27年度 植物工場勉強会
植物工場の品質・衛生管理ポイント
はじめに
植物工場野菜をサラダやサンドイッチといった中食の原材料として供給する場合の、植物工場の品質管理・衛生管理について考えます。
植物工場ビタミンファームの設備と品質管理
2020年新型コロナウイルス感染症流行により国内の移動が制限された中で、食品業界誌から取材要請をいただきオンライン工場見学を企画した。以下はWeb通信システムを通じてオンラインで見たビタミンファームの栽培、出荷、生産管理の様子のレポートである。
オフィス設計
ABW (Activity Based Working) オフィス設計
2020年以降主流となった勤務時間やミーティングをフレキシブルな環境でサポートするフリーアドレスをベースとしたオフィスを設計します。植栽、音、什器の触感でリラックスしながら、集中度の高い作業に適した空間を提供します。
セミナーレポート
セミナー
食品安全や植物工場に関するセミナーを開催しています。
フードセーフティージャパン2025 FF01設計者に求められる食品安全
2025年10月 食品工場設計/異物混入防止/農業規格JGAPのセミナーをFOOD展主催者セミナーとして企画しました。具体的な事例を示し、多くの聴講者から好評価をいただきました。
フードセーフティージャパン2025 FS06JGAP/セブン-イレブン・ジャパンのの取り組み
2025年10月 食品工場設計/異物混入防止/農業規格JGAPのセミナーをFOOD展主催者セミナーとして企画しました。具体的な事例を示し、多くの聴講者から好評価をいただきました。
フードセーフティージャパン2025 FS07 異物混入防止
2025年10月 食品工場設計/異物混入防止/農業規格JGAPのセミナーをFOOD展主催者セミナーとして企画しました。具体的な事例を示し、多くの聴講者から好評価をいただきました。
フードセーフティージャパン2023 パネルディスカッション
2023年9月にコーディネートしたフードセーフティージャパン主催者セミナーのサマリーと資料の一部です。
第28回SHITAシンポジウム(2018.1.15)講演要旨(PDF版)
2018年1月に登壇した植物工場のオぺレーション/品質管理に関する講演の資料を掲載しています。
電気設備学会誌寄稿 植物工場(完全閉鎖型)の電気設備と野菜栽培
2020年10月電気設備学会誌に掲載された植物工場のコラムを掲載しています。
事務所概要
| 名 称 | 岡安設計事務所 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都大田区 |
| 代 表 | 岡安晃一 |
| 連絡先 | 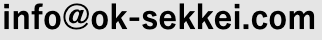 |
- 岡安晃一 経歴
- 二級建築士
- 基本情報技術者
- JFS-A/B監査員資格
- ISO22000監査員講習修了
- JGAP監査員補
- 食品安全委員会 食品安全モニター
- 一級管工事施工管理技士
- 空調換気改修設計
- 結露調査・改修
- 恒温恒湿庫設計
- 発酵庫設計
- 動物検疫施設設計
- 植物工場設備設計
- マルチセンシングシステム設計
- 野菜原材料マーケティング
- 野菜洗浄・加工設備設計